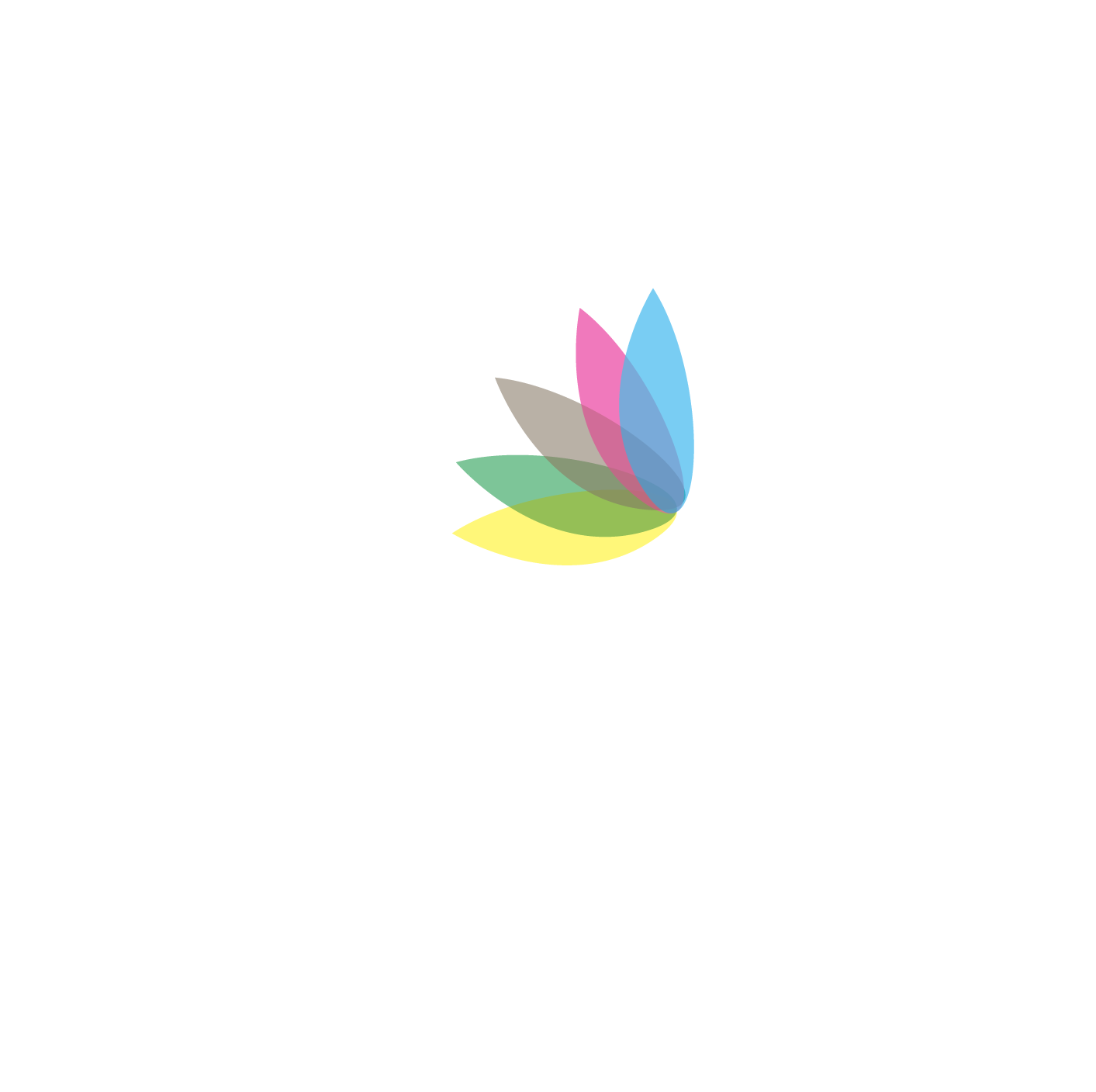日本書紀に書いてある木の話を、一つだけ知っておきましょう
日本書紀に書いてある木の話を、一つだけ知っておきましょう
あなたがこの話知っているだけで、心豊かになれます。木の話続きます。
日本書紀には、「社(やしろ)には檜(ヒノキ)を、船には楠(クスノキ)や杉を、そして人間が最後にお世話になる棺(ヒツギ)には槇(マキ)を使う」と記されているそうです。
ヒノキは耐久性があって品格もあることから、建物に使い、クスや杉は水に強いから、船をつくるのに適している。江戸の天馬船(テンマセン)は全部杉でできていたらしく、古代エジプトの太陽の船と呼ばれた木造船も、レバノンあたりで伐採した杉を使っていたという事らしい。
古代、日本も土葬という(現代は火葬が主)風習もあり、棺に入れて土中に埋め弔った。棺には腐りにくい木、忘れがたい人をいつまでも守って欲しいという願いもあったのでしょう、丈夫な槇を使っていたと。どうやって知っていったのか、それぞれの木の特徴をね。それが今にずっとつながっているというのも人間の能力は本当に素晴らしいと感服するのであります。
北陸地方には、「家を建て庭をつくるとき、槇の木を植える」という慣わしがあるそうです。慣わしをたどるのもおもしろそうですね。
「木と生きる、木を活かす」-木地師千年の知恵と技-・・・とのサブタイトルがついている川北良造(人間国宝)師著書から引用しています。
いずれにしても、2000年以上も前からも、私たち祖先は、各木の性質を知り、適材適所使いこなしてきているという驚愕の事実。神社仏閣をはじめとして、木というものに出会う時、グーグルレンズをあてて、検索ボタンを押してみてみて下さい。検索拾ってくれるかな?きっとまた、自然の神秘と先祖の叡知に出会えると思います。木材屋さんがヒットしたりなんかして(笑)。でも余り、スマホをあててやっっていると、怪しいひとに間違えられるかもしれませんので、ほどほどにね。
お茶の木でつくったのペン数々。ドクロ////万年筆です(怖)

関連記事
TEWOFURU ~テヲフル~|「世界の憧れ」
1,300年ジュエリー文化がなかった日本。しかしながら、この長い歴史と文化によって育まれた日本美には特有のものがあります。「着物」に負けない、たおやかなる日本女性美、戦火の中でも美しく散った勇壮な武将たち。TEWOFURUテヲフルでは、培われた伝統を生かし、『『和』となって遊ぼ~」を標榜し世界アート文化を取り込んで今風にアレンジ、主として現代漆を駆使した木工アイテムの関連開発に挑んでいます。仮説や、仮定そして邂逅の夢物語りで新たなアイテムとのかかわりの楽しみを創出していきます。指輪、イヤーカフ、ほか宝飾品、各種ペン、キャラクターなど木工関連小物グッズ開発を進めていきます、何かしら皆様の心の支えともなれば、本望でございます。
「違いは美しさを育み、未来の扉を開く」
| 屋号 | TEWOFURU |
|---|---|
| 住所 | 〒843-0301 佐賀県嬉野市嬉野町大字下宿甲4719-2 |
| 電話番号 | 070-8432-4343 |
| 営業時間 | 平日11時~17時 |
| 代表者名 | 山口 進一郎 |
| info@tewofuru.com |